ローコスト住宅の気密性は低い?高気密高断熱で後悔しない方法

「マイホームは欲しいけど、予算は限られている…」
「ローコスト住宅って、性能が低くて冬は寒いんじゃないの?」
初めての家づくりを考える多くの方が、このような期待と不安を抱えています。特に、1000万円台から建てられるローコスト住宅は魅力的ですが、「安かろう悪かろう」ではないかと心配になるのは当然のことです。
この記事では、住宅の専門知識を持つプロのSEOライターが、ローコスト住宅の「気密性」に焦点を当て、限られた予算内で快適な高気密高断熱住宅を実現するための具体的な方法を徹底解説します。
この記事を読めば、価格を抑えながらも暖かく快適な家を建てるための知識が身につき、後悔しないハウスメーカー・工務店選びができるようになります。く快適なマイホームを実現するための第一歩を踏み出せるはずです。
この記事の目次
結論ローコスト住宅でも高気密高断熱は可能
まず結論からお伝えします。ローコスト住宅でも、高い気密性と断熱性を備えた快適な家を建てることは十分に可能です。
「ローコスト=性能が低い」というイメージは、必ずしも正しくありません。大切なのは、価格と性能のバランスを正しく理解し、適切な会社を選ぶことです。
性能と価格のバランスが重要
ローコスト住宅は、広告宣伝費の削減、建材の大量仕入れ、設計や仕様の規格化など、様々な工夫によって低価格を実現しています。
重要なのは、どこでコストを削減しているかです。住宅の快適性や耐久性に直結する「気密・断熱」といった基本性能に妥協せず、こだわりを持って家づくりをしている会社を選ぶことが、成功の鍵となります。
ローコスト住宅が寒いと言われる理由
では、なぜ「ローコスト住宅は寒い」というイメージが根強いのでしょうか。その理由は、一部の住宅会社がコストを優先するあまり、以下のような部分で仕様を下げてしまうことがあるためです。
- 断熱材の厚みが不十分、または性能の低い断熱材を使用している
- 熱が逃げやすいアルミサッシの窓を標準仕様にしている
- 職人の手間がかかる「気密施工」が丁寧に行われていない
これらの積み重ねが、冬は寒く夏は暑い、快適とは言えない家につながってしまいます。しかし、これは一部のケースであり、すべてのローコスト住宅が寒いわけではありません。
ハウスメーカー・工務店選びが鍵
快適なローコスト住宅を実現できるかどうかは、どのハウスメーカーや工務店に依頼するかにかかっています。
近年では、ローコストでありながら高い住宅性能を強みとする会社が増えています。この記事で紹介するポイントを押さえて会社選びをすれば、予算内で理想の「高気密高断熱住宅」を手に入れることができるでしょう。
まず知りたい気密・断熱性能の基礎知識
ハウスメーカーのカタログやウェブサイトを見ていると、「C値」「UA値」といった専門用語が出てきます。これらは住宅性能を客観的に示す重要な指標です。難しく感じるかもしれませんが、基本的な意味さえ理解すれば、家づくりの大きな武器になります。
気密性を示すC値とは
C値(相当隙間面積)とは、
家にどれくらいの隙間があるかを示す数値です。床面積1㎡あたりに存在する隙間の面積(㎠)で表され、この数値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高い家であることを意味します。
気密性が高いと、以下のようなメリットがあります。
- 外気の侵入が減り、冷暖房が効きやすくなる(省エネ)
- 計画的な換気が正しく機能し、常に新鮮な空気を保てる
- 壁の中の結露(内部結露)を防ぎ、家の寿命を延ばす
一般的に、快適な暮らしのためにはC値1.0㎠/㎡以下が一つの目安とされています。高性能な住宅会社では、0.5㎠/㎡以下を基準にしているところも少なくありません。
断熱性を示すUA値とは
UA値(外皮平均熱貫流率)とは、
家の壁や屋根、窓など(外皮)から、どれだけ熱が逃げやすいかを示す数値です。この数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性が高い家であることを意味します。
UA値が小さい家は、外の暑さや寒さの影響を受けにくいため、「夏は涼しく、冬は暖かい」快適な室温を保ちやすくなります。
国が推奨するHEAT20 G1・G2基準
UA値の具体的な目標としては、国が定める省エネ基準の他に、より高いレベルを目指す「HEAT20」という基準があります。
- G1グレード
省エネ基準よりもワンランク上の断熱性能。冬、無暖房の部屋でも室温が概ね10℃を下回らないレベル。 - G2グレード
G1よりもさらに上の断熱性能。冬、無暖房の部屋でも室温が概ね13℃を下回らないレベル。
多くの高性能住宅では、このG2グレードを目標に掲げています。お住まいの地域によって基準値は異なりますが、ハウスメーカーを選ぶ際には、HEAT20のどのグレードに対応しているかを確認するのも良い方法です。
(参考:一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会)
高気密高断熱を実現する3つの重要ポイント
限られた予算の中で高い住宅性能を実現するには、どこにお金をかけるべきか、その優先順位を理解することが大切です。特に重要なのが「断熱材」「窓」「気密施工」の3つです。
断熱材の種類と選び方
断熱材は、家の快適性を左右する心臓部です。ローコスト住宅でよく使われる代表的な断熱材には、以下のようなものがあります。
- グラスウール
ガラス繊維でできた、最もポピュラーな断熱材。コストパフォーマンスに優れていますが、湿気に弱いため、丁寧な防湿・気密施工が不可欠です。 - ロックウール
玄武岩などを原料とする鉱物繊維の断熱材。性能はグラスウールと似ていますが、耐火性や吸音性に優れています。 - 現場発泡ウレタンフォーム(吹付断熱)
現場で液体をスプレー状に吹き付け、発泡・硬化させる断熱材。細かい隙間にも充填しやすく、高い気密性を確保しやすいのが特徴です。
どの断熱材が良い・悪いということではなく、それぞれの特性を理解し、正しく施工することが最も重要です。
窓・サッシの性能と選び方
家の中で最も熱の出入りが激しい場所は「窓」です。窓の性能を高めることは、断熱性を向上させる上で非常に効果的です。
- サッシ(窓枠)の素材
従来のローコスト住宅ではコストの安い「アルミサッシ」が主流でしたが、熱を伝えやすいため結露の原因になります。断熱性の高い「樹脂サッシ」や、外側がアルミで室内側が樹脂の「アルミ樹脂複合サッシ」を選ぶようにしましょう。 - ガラスの種類
ガラスも、1枚の「単板ガラス」ではなく、2枚のガラスの間に空気層がある「ペアガラス(複層ガラス)」が最低限の基準です。より性能を求めるなら、3枚のガラスを使った「トリプルガラス」や、特殊なガスが封入された「Low-E複層ガラス」がおすすめです。
隙間をなくす気密施工の重要性
どんなに高性能な断熱材や窓を使っても、家に隙間があればその効果は半減してしまいます。高気密を実現するために欠かせないのが、職人による丁寧な「気密施工」です。
柱と断熱材の隙間、コンセントボックスの周り、配管が壁を貫通する部分など、隙間ができやすい箇所を専用の気密テープやシートで丁寧に塞いでいく作業が求められます。この手間を惜しまない会社こそ、本当に性能を重視している会社と言えるでしょう。
高性能なローコスト工務店の探し方
大手ハウスメーカーだけでなく、地域に根差した工務店の中にも、驚くほど高性能な家を適正価格で建てる会社がたくさんあります。優良な工務店を見つけるには、以下の方法が有効です。
- 「完成見学会」や「構造見学会」に参加する
実際に建てた家や、建築途中の構造(断熱材の施工状態など)を自分の目で確かめるのが一番です。 - C値・UA値の実績を確認する
「C値●●以下を保証」「UA値はHEAT20 G2基準です」など、性能値を具体的に示している会社は信頼できます。 - 社長や設計士の家づくりへの想いを聞く
性能へのこだわりや哲学を持っている会社は、見えない部分まで丁寧に仕事をしてくれる可能性が高いです。
予算1000万円台で高性能住宅を建てるコツ
「予算1000万円台でも、性能に妥協したくない!」という方は、設計や仕様決めで少し工夫が必要です。コストを抑えつつ性能を確保するための3つのコツをご紹介します。
シンプルな総二階・凹凸の少ない間取り
家の形は、できるだけシンプルな箱型(総二階)に近づけるのがポイントです。
凹凸の多い複雑な形状の家は、外壁の面積が増えるため、材料費も工事費も高くなります。また、角が増えることで断熱材の施工が難しくなり、熱が逃げる「熱橋(ヒートブリッジ)」のリスクも高まります。シンプルな間取りは、コストダウンと性能アップの両方に貢献します。
オプションと標準仕様の見極め
ローコスト住宅では、魅力的な価格が提示されていても、快適に住むための設備がオプション扱いになっているケースがあります。
契約前に「どこまでが標準仕様で、どこからがオプションなのか」を徹底的に確認しましょう。特に、断熱材のグレードアップや樹脂サッシへの変更がオプションの場合、最終的な金額が大きく膨らむ可能性があります。標準仕様のままで十分な性能が確保されている会社を選ぶことが重要です。
性能に関わる部分に予算を集中させる
家づくりでは、予算配分のメリハリが大切です。キッチンやお風呂などの住宅設備、壁紙などの内装は、後からでもリフォームで変更できます。
しかし、断熱材や窓、家の構造といった基本性能は、後から変更するのが非常に困難で、コストもかかります。限られた予算は、まず「断熱・気密・耐震」といった、家の骨格となる部分に優先的に使いましょう。
契約前に確認!後悔しないためのチェックリスト
理想の会社が見つかったら、契約前に最終確認をしましょう。口約束ではなく、必ず書面で確認することが大切です。
気密測定の実施とC値の保証
- 「全棟で気密測定を実施していますか?」
- 「測定したC値の結果は報告してもらえますか?」
- 「目標とするC値の保証はありますか?」
断熱材やサッシの標準仕様
- 「標準仕様の断熱材の種類と厚みを教えてください」
- 「標準仕様の窓は、樹脂サッシですか?ガラスの種類は何ですか?」
- 「UA値はいくつですか?HEAT20のどのグレードに相当しますか?」
換気システムの種類と性能
- 「換気システムは第一種換気ですか、第三種換気ですか?」
- 「(第一種の場合)熱交換機能はついていますか?」
建築実績と施主の口コミ
- 「これまで建てた家のC値やUA値の実績を見せてもらえますか?」
- 「実際に住んでいる方の感想や評判を聞くことはできますか?」
ローコスト住宅の気密性に関するQ&A
最後に、ローコスト住宅の気密性に関してよくある質問にお答えします。
長期優良住宅の認定は可能か?
はい、ローコスト住宅でも長期優良住宅の認定を受けることは可能です。
長期優良住宅は、耐震性や省エネ性など、いくつかの項目で高い基準をクリアする必要があります。タマホームのように標準で対応している会社もあれば、オプションで対応する会社もあります。認定には申請費用などが別途かかる場合があるため、総額を確認しておきましょう。
床暖房は設置すべきか?
高気密高断熱住宅の場合、必ずしも床暖房が必要とは限りません。
家全体の断熱性が高いため、エアコン1台で家中が十分に暖かくなるケースも多いからです。床暖房は設置コストもランニングコストもかかるため、本当に必要かどうかは、住宅会社の担当者と相談しながら慎重に検討しましょう。むしろ、性能の低い家で床暖房に頼るよりも、家の基本性能を高めることにお金を使った方が、結果的に光熱費を抑えられます。
平屋でも高気密高断熱は実現できるか?
はい、もちろん平屋でも高気密高断熱住宅は実現できます。
基本的な考え方は二階建てと同じで、断熱・気密・窓の性能を高めることが重要です。ただし、平屋は二階建てに比べて屋根と基礎の面積が広くなるため、同じ延床面積の場合、断熱にかかるコストが少し割高になる傾向があります。
まとめ
今回は、ローコスト住宅の気密性について、性能の基礎知識から具体的な会社選びのポイントまで詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- ローコスト住宅でも高気密高断熱は実現できる
- 性能を判断するには「C値」「UA値」を理解することが重要
- 快適な家は「断熱材」「窓」「気密施工」の3つが鍵を握る
- 性能にこだわるハウスメーカーや工務店をしっかり選ぶ
- 契約前には「気密測定の有無」や「標準仕様」を必ずチェックする
「安かろう悪かろう」の家づくりで後悔しないために、ぜひこの記事で得た知識を活用してください。価格だけでなく、性能という「ものさし」を持って会社選びをすることで、きっと予算内で満足のいく、暖かく快適なマイホームが実現できるはずです。
この記事の担当:

豊栄建設家づくり編集部
家づくりのヒントや住まいの最新情報を分かりやすくご紹介。皆さまの理想の住まいづくりにお役立てください。
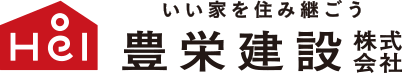

 資料請求
資料請求


 見学ご予約
見学ご予約


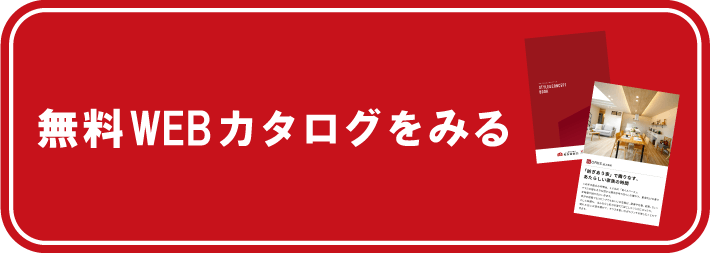
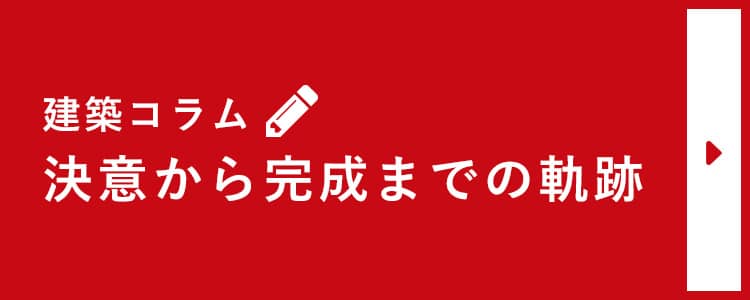









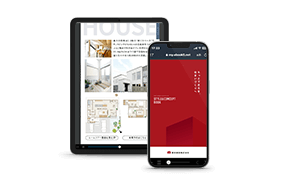




 Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram YouTube
YouTube

