家屋解体費用の相場と内訳!一軒家の坪単価・安くするコツ

「実家を相続したけれど、古くて住めそうにない…」「家の建て替えを考えているけど、まず解体にいくらかかるんだろう?」
大切な家を解体するとなると、多くの方がまず気になるのが「家屋解体費用」ではないでしょうか。一体いくらくらいかかるのか、何にどれくらい費用が発生するのか、見当もつかないと不安になりますよね。
この記事では、そんな不安を解消するために、家屋解体費用の相場から、費用の内訳、費用が変動する要因、そして気になる解体費用を安く抑えるコツまで、専門知識を持つプロのSEOライターが徹底解説します。ぜひ最後までご覧ください。
家屋解体費用の相場
家屋解体費用と一口に言っても、建物の構造や大きさ、立地条件などによって金額は大きく変動します。まずは、一般的な費用の相場観を掴んでいきましょう。
構造別費用相場 木造・鉄骨・RC造
建物の構造によって、解体の手間や処分する廃材の種類が異なるため、費用相場も変わってきます。主な構造別の坪単価の目安は以下の通りです。
- 木造(W造)
坪単価 3万円~5万円程度。一般的な戸建て住宅に多く、比較的解体しやすいため費用は抑えめです。 - 鉄骨造(S造)
坪単価 4万円~7万円程度。木造に比べて頑丈なため、解体に手間と時間がかかり、太い鉄骨は切断も必要になるため費用が上がります。軽量鉄骨造と重量鉄骨造があり、重量鉄骨造の方が高くなる傾向があります。 - 鉄筋コンクリート造(RC造)
坪単価 6万円~8万円程度。非常に頑丈な構造で、解体には大型重機や特殊な工法が必要となるため、最も費用が高くなります。廃材のコンクリートガラも重量があり、処分費用も高額になりがちです。
これらの坪単価はあくまで目安であり、解体業者や地域、建物の状態によって変動します。
坪数別解体費用の目安 30坪・50坪
構造別の坪単価をもとに、具体的な坪数での解体費用総額の目安を見てみましょう。
- 30坪の家屋の場合
- 木造:90万円~150万円程度 (30坪 × 3万~5万円)
- 鉄骨造:120万円~210万円程度 (30坪 × 4万~7万円)
- RC造:180万円~240万円程度 (30坪 × 6万~8万円)
- 50坪の家屋の場合
- 木造:150万円~250万円程度 (50坪 × 3万~5万円)
- 鉄骨造:200万円~350万円程度 (50坪 × 4万~7万円)
- RC造:300万円~400万円程度 (50坪 × 6万~8万円)
これらは本体工事費の目安であり、後述する付帯工事費や諸経費が別途かかる場合があります。
地域による費用相場の違いとは
解体費用は、地域によっても差が出ることがあります。一般的に、都市部の方が地方に比べて高くなる傾向があります。
主な理由としては、以下のような点が挙げられます。
- 人件費の違い
都市部の方が作業員の人件費が高い傾向にあります。 - 廃棄物処理費用の違い
廃棄物処理場の処理費用が地域によって異なるため、これが解体費用に影響します。 - 運搬費用の違い
都市部では交通渋滞や狭い道路が多く、廃材の運搬効率が悪くなり、運搬費用が割高になることがあります。 - 需要と供給のバランス
解体業者の数や競争状況によっても価格は変動します。
一軒家の解体費用総額の目安
一般的な一軒家(木造2階建て、延床面積30坪程度)の解体費用総額は、おおよそ100万円~200万円程度が目安となります。
ただし、これはあくまで標準的なケースであり、アスベストの有無、残置物の量、外構(ブロック塀やカーポートなど)の解体の有無などによって、費用は大きく変動します。正確な費用を知るためには、必ず複数の解体業者に見積もりを依頼しましょう。
解体費用の内訳を徹底解説
家屋の解体費用は、大きく分けて「本体工事費」「付帯工事費」「廃棄物処理運搬費」「諸経費」の4つで構成されています。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
本体工事費 足場・養生・解体作業
本体工事費とは、建物そのものを取り壊すためにかかる費用です。
主な内容は以下の通りです。
- 仮設工事費
- 足場の設置
安全に作業を進めるため、また、騒音や粉塵の飛散を抑えるために建物の周囲に足場を組みます。 - 養生シートの設置
足場の周りを養生シートで覆い、騒音やホコリが近隣に迷惑をかけるのを防ぎます。
- 足場の設置
- 解体作業費
建物の屋根、壁、柱、基礎などを重機や手作業で解体していく作業の費用です。建物の構造や規模によって変動します。
付帯工事費 アスベスト・樹木伐採
付帯工事費とは、建物本体の解体以外に発生する工事の費用です。
具体的には以下のようなものがあります。
- 建物以外の解体・撤去費用
- ブロック塀、フェンス、門扉、カーポート、物置などの撤去
- 庭木、庭石の撤去・処分
- 井戸の埋め戻し、浄化槽の撤去・処分
- アスベスト除去費用
建物にアスベストが使用されている場合、専門の知識と技術を持った作業員による除去作業が必要となり、別途高額な費用が発生します。 - 室内残置物撤去費用
家の中に残された家具や家電、不用品などの処分費用です。
これらの付帯工事は、必要な場合のみ発生する費用です。
廃棄物処理運搬費 木くず・ガラ
解体工事では、木くず、コンクリートガラ、鉄くず、プラスチック、ガラスなど、様々な種類の廃棄物が発生します。廃棄物処理運搬費とは、これらの廃棄物を分別し、法律に基づいて適切に処理場へ運搬・処分するための費用です。
廃棄物の種類や量、処分場の距離などによって費用は変動します。不法投棄は絶対に許されないため、信頼できる業者はこの費用を適正に見積もりに含んでいます。
諸経費 書類作成・近隣挨拶
諸経費とは、上記以外で解体工事を進めるために必要な経費のことです。
主な内容としては、以下のようなものがあります。
- 各種申請書類作成・届出費用
建設リサイクル法に基づく届出や、道路使用許可申請など、行政への手続きにかかる費用です。 - 近隣挨拶費用
工事前に近隣住民へ挨拶回りを行う際の粗品代などが含まれる場合があります。 - 現場管理費
工事現場の管理や安全対策にかかる費用です。 - 重機回送費
解体に使用する重機を現場まで運搬し、工事後に搬出するための費用です。 - 駐車場代
作業車両の駐車スペースがない場合に、近隣のコインパーキングなどを利用する際の費用です。 - 保険料
工事中の万が一の事故に備えるための損害保険料などです。
諸経費は業者によって計上方法が異なる場合があるため、見積もり時に内容を確認することが大切です。
解体費用が変動する主な要因
家屋の解体費用は、様々な要因によって大きく変動します。どのような点が費用に影響するのか、具体的に見ていきましょう。
建物の構造と材質 木造・鉄骨造
前述の通り、建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)は費用を左右する大きな要因です。
木造は比較的解体が容易で廃材も処理しやすいため安価ですが、鉄骨造は鉄骨の切断、RC造はコンクリートの破砕などが必要となり、手間とコストがかかります。また、使用されている建材の種類や量によっても、廃材の処分費用が変わってきます。
建物の坪数と階数
当然ながら、建物の坪数(延床面積)が大きくなるほど、また階数が多くなるほど、解体する範囲が広がり、作業量も増えるため、費用は高くなります。屋根や壁、床などの面積が増え、廃材の量も多くなるためです。
立地条件と周辺環境 道幅・重機
建物の立地条件や周辺環境も、解体費用に大きく影響します。
- 前面道路の道幅
道幅が狭く、大型のトラックや重機が現場に入れない場合は、小型の重機を使用したり、手作業での解体や廃材の搬出が増えたりするため、作業効率が落ち、人件費や運搬費が割高になることがあります。 - 重機の使用可否
重機が使用できないような狭小地や、住宅密集地では、手作業の割合が増えるため費用が上昇します。 - 近隣との距離
隣家との距離が近い場合は、騒音や振動、粉塵の飛散に通常以上に配慮する必要があり、養生をより厳重にするなど追加の対策が必要になることがあります。 - 電線や障害物の有無
敷地内や上空に電線や障害物がある場合、作業に制限が出たり、特別な対策が必要になったりして費用が加算されることがあります。
アスベスト含有建材の有無と処理
アスベスト(石綿)とは、かつて耐火性や断熱性に優れていることから建材に広く使用されていましたが、健康被害のリスクが明らかになり、現在は原則として使用が禁止されています。
もし解体する建物にアスベスト含有建材が使用されている場合、専門の業者による厳重な管理下での除去作業が必要となり、通常の解体費用に加えて高額なアスベスト除去費用が発生します。アスベストのレベル(発じん性の高さ)や使用箇所、範囲によって費用は大きく変動します。
家屋内の残置物の量と処分
家の中に家具、家電、衣類、布団、食器などの残置物が多く残っている場合、その処分費用が別途発生します。
解体業者に処分を依頼することも可能ですが、一般廃棄物収集運搬の許可を持つ業者か、提携業者に委託することになるため、費用が割高になる傾向があります。事前に自分で処分できるものは片付けておくことで、この費用を抑えることができます。
付帯工事の有無 井戸・浄化槽
建物本体以外にも解体・撤去が必要なものがある場合、それらは付帯工事として費用が発生します。
- 庭木・庭石の撤去
- ブロック塀・フェンス・門扉の解体
- カーポート・物置の解体
- 井戸の埋め戻し・お祓い
- 浄化槽の撤去・清掃・処分
- 駐車場のコンクリートやアスファルトの解体(斫り工事)
これらの付帯工事の有無と規模によって、総額は大きく変わります。
追加費用が発生するケース
見積もり時には想定されていなかった事態が発生し、追加費用がかかるケースもあります。
- 地中埋設物の発見
解体工事を進めていく中で、地中から以前の建物の基礎、コンクリートガラ、浄化槽、井戸、大きな石などが発見されることがあります。これらの撤去・処分には追加費用が発生します。 - 土壌汚染の発見
万が一、土壌汚染が発見された場合は、その浄化費用が別途必要になります。 - 想定外のアスベスト発見
事前の調査で見つからなかった箇所からアスベストが発見された場合、追加の除去費用が発生します。
追加費用が発生する可能性については、契約前に業者に確認しておくことが重要です。
家屋解体工事の流れと期間
実際に家屋解体工事を依頼する場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。一般的な手順と期間の目安を解説します。
解体工事前の準備 業者選定・契約
- 解体業者の選定
複数の業者に相談し、現地調査を依頼します。 - 現地調査・見積もり取得
業者が実際に現地を訪れ、建物の状況や周辺環境を確認し、見積書を作成します。 - 見積書の比較検討
複数の業者から見積もりを取り、内容や金額、対応などを比較検討します。 - 契約締結
依頼する業者が決まったら、工事請負契約を締結します。契約内容(工事範囲、金額、工期、支払い条件、追加費用発生時の対応など)をしっかり確認しましょう。
各種届出の手続き 建設リサイクル法
解体工事を行う際には、いくつかの法的な届出が必要です。
- 建設リサイクル法に基づく届出
延床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。通常は解体業者が代行してくれます。 - 道路使用許可申請
工事車両の駐車や資材の搬出入などで道路を使用する場合、管轄の警察署に申請が必要です。 - 特定建設作業実施届出
騒音規制法や振動規制法に基づき、指定された地域で特定の重機を使用する場合、市区町村への届出が必要な場合があります。
これらの手続きは、多くの場合、解体業者が代行してくれますが、施主としてどのような届出が必要なのか把握しておくと安心です。
解体工事の実施 足場・内装・本体
- 近隣への挨拶
工事開始前に、解体業者とともに近隣住民へ工事内容や期間などを説明し、挨拶回りを行います。 - 足場・養生の設置
建物の周囲に足場を組み、防音シートや防塵シートで養生します。 - 内装材の撤去(分別解体)
畳、建具、断熱材、石膏ボードなど、手作業で分別しながら内装材を撤去します。 - 屋根材の撤去
瓦などの屋根材を撤去します。 - 建物本体の解体
重機を使って、壁、柱、梁などの構造材を解体していきます。散水しながら作業し、粉塵の飛散を抑えます。 - 基礎の解体・撤去
建物の基礎部分を掘り起こし、解体・撤去します。 - 廃材の分別・搬出
解体で発生した木くず、コンクリートガラ、鉄くずなどを種類ごとに分別し、トラックで処理場へ搬出します。
工事完了後の整地と清掃
- 地中確認
地中に障害物(コンクリート片など)が残っていないか確認します。 - 整地
重機や手作業で土地を平らにならします。整地の程度(粗整地、更地渡しなど)は契約内容によります。 - 清掃
現場周辺を清掃し、工事完了となります。 - 施主による最終確認
工事が契約通りに行われたか、施主が立ち会い確認します。
解体工事にかかる期間の目安
一般的な木造2階建て30坪程度の家屋の場合、解体工事にかかる期間の目安は、準備期間を除いて1週間~2週間程度です。
ただし、これは天候に恵まれ、順調に進んだ場合の目安です。建物の規模、構造、立地条件、アスベスト除去の有無、天候などによって期間は変動します。
鉄骨造やRC造の場合は、さらに長い期間が必要になります。
解体費用の見積もりと業者の選び方
適正な価格で、安心して任せられる解体業者を選ぶことは非常に重要です。見積もり取得時の注意点と、優良な業者の見極め方を解説します。
見積書で確認すべき項目 範囲・単価
解体業者から見積書を受け取ったら、以下の項目をしっかり確認しましょう。
- 工事範囲の明確さ
どこからどこまでが工事に含まれているのか(建物本体のみか、外構も含むのか、残置物処分は含まれるかなど)が明記されているか。 - 各項目の単価と数量
「一式」という記載だけでなく、可能な限り各作業項目(足場設置、養生、内装解体、本体解体、基礎撤去、廃棄物処理など)の単価、数量、金額が具体的に記載されているか。 - 廃棄物処理費の内訳
どのような種類の廃棄物がどれくらい発生し、その処理費用がいくらなのかが分かるようになっているか。 - 諸経費の内容
諸経費に何が含まれているのか、不明な場合は説明を求めましょう。 - 追加費用発生の条件
どのような場合にいくら程度の追加費用が発生する可能性があるのか、明記されているか、または説明があるか。 - 有効期限
見積書の有効期限が記載されているか。
不明な点や疑問点は遠慮なく業者に質問し、納得できるまで説明を求めることが大切です。
相見積もりを取る重要性
解体費用は業者によって大きく異なることがあります。そのため、必ず複数の業者(できれば3社以上)から見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。
相見積もりをすることで、以下のメリットがあります。
- 費用の適正価格が把握できる
複数の見積もりを比較することで、その工事内容に対するおおよその相場観が分かります。 - 不当に高い、または安すぎる業者を見抜ける
極端に高い見積もりや、逆に安すぎる見積もり(手抜き工事や不法投棄のリスクがある)を提示する業者を避けることができます。 - 価格交渉の材料になる
他社の見積もりを提示することで、価格交渉がしやすくなる場合があります。 - 業者の対応や提案力を比較できる
見積もり依頼時の対応の速さや丁寧さ、提案内容なども比較検討できます。
手間はかかりますが、相見積もりは適正価格で信頼できる業者を選ぶために不可欠なステップです。
優良な解体業者の見極め方
安心して工事を任せられる優良な解体業者を見極めるためには、以下のポイントをチェックしましょう。
- 建設業許可または解体工事業登録の有無
500万円以上の解体工事を請け負う場合は「建設業許可(とび・土工工事業または解体工事業)」が、500万円未満の場合は「解体工事業登録」が必要です。必ず確認しましょう。 - 実績と経験
同種・同規模の建物の解体実績が豊富か、ホームページや直接の質問で確認しましょう。 - 保険への加入状況
工事中の事故に備えて、損害賠償保険(請負業者賠償責任保険など)に加入しているか確認しましょう。 - 見積書の内容が詳細で明確か
前述の通り、見積もりの内訳が具体的で分かりやすいか。 - 担当者の対応が誠実で丁寧か
質問に対して的確に答えてくれるか、説明が分かりやすいか、親身になって相談に乗ってくれるかなど、担当者の人柄や対応も重要です。 - マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行
廃棄物が適正に処理されたことを証明する「マニフェスト」をきちんと発行してくれるか確認しましょう。これは不法投棄を防ぐための重要な書類です。 - 近隣への配慮
工事前の近隣挨拶や、工事中の騒音・振動・粉塵対策などをしっかり行ってくれるか。
悪徳業者に注意!トラブル事例
残念ながら、解体業界にも悪徳業者が存在します。以下のようなトラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。
- 不当な高額請求
相場よりもはるかに高い金額を見積もられたり、契約後に不当な追加費用を請求されたりするケース。 - 契約内容と異なる工事
見積もりに含まれていたはずの工事が行われない、手抜き工事をされるなど。 - 不法投棄
解体で出た廃棄物を山林や空き地に不法投棄する。これは施主も責任を問われる可能性があります。 - 近隣トラブルへの無対応
工事中の騒音や振動で近隣からクレームが出ても、誠実に対応しない。 - 工事の中断・放棄
契約金だけ受け取って工事を始めない、途中で放棄してしまう。
「あまりにも安すぎる見積もり」や「契約を急がせる業者」には特に注意が必要です。
家屋解体費用を安く抑えるコツ
家屋の解体にはまとまった費用がかかりますが、工夫次第で少しでも安く抑えることが可能です。ここでは、そのための具体的なコツをご紹介します。
家財道具・不用品の事前処分
家の中に残っている家具、家電、衣類、書籍などの家財道具や不用品は、可能な限り自分で事前に処分しておきましょう。
解体業者に処分を依頼すると、一般的に「産業廃棄物」としての扱いになるか、提携する一般廃棄物収集運搬業者への委託費用が上乗せされるため、割高になることが多いです。
自治体の粗大ごみ収集を利用したり、リサイクルショップやフリマアプリで売却したり、不用品回収業者に依頼したりするなど、自分で処分することで残置物処分費用を大幅に削減できます。
解体工事の時期を選ぶ 閑散期
解体業者にも繁忙期と閑散期があります。一般的に、年度末(2月~3月)や年末は公共工事や企業の決算期が重なり、繁忙期となる傾向があります。
逆に、梅雨時期(6月~7月)や夏場(8月)などは比較的工事が少なく、閑散期となることがあります。
閑散期に依頼することで、業者のスケジュールに余裕があり、費用交渉がしやすくなったり、値引きに応じてくれたりする可能性があります。ただし、天候に左右される工事なので、梅雨時期は工期が延びるリスクも考慮しましょう。
複数業者への見積もり依頼と比較
これは最も基本的かつ効果的な方法です。必ず3社以上の解体業者に相見積もりを依頼しましょう。
各社の見積もり内容を詳細に比較することで、費用の内訳や適正価格が見えてきます。また、他社の見積もりを提示することで、価格交渉の材料としても活用できます。
ただし、単に安いだけでなく、工事内容や信頼性も総合的に判断することが重要です。
自治体の補助金・助成金制度活用
お住まいの自治体によっては、老朽化した空き家の解体や、耐震性の低い危険な建物の解体に対して、補助金や助成金制度を設けている場合があります。
制度の有無や条件、補助金額は自治体によって異なります。まずは、市区町村の役所の建築指導課や空き家対策担当課などに問い合わせてみることをおすすめします。
(例:〇〇市 空き家解体 補助金 で検索)
補助金制度を活用できれば、解体費用を大幅に軽減できる可能性があります。
分離発注によるコスト削減検討
解体工事に関連する作業を、すべて一括で1つの業者に依頼するのではなく、作業ごとに専門業者に個別に依頼する「分離発注」という方法も、コスト削減につながる場合があります。
例えば、
- 家屋の解体工事は解体専門業者へ
- 家財道具の処分は不用品回収業者へ
- 樹木の伐採は造園業者へ
といった形です。中間マージンが発生しないため、総額を抑えられる可能性があります。
ただし、各業者との連絡や調整、スケジュール管理などを自分で行う必要があり、手間が増えるというデメリットもあります。時間と労力に余裕がある場合に検討してみましょう。
解体後の手続きと注意点
家屋の解体工事が無事に完了した後にも、いくつか必要な手続きや注意点があります。
建物滅失登記の手続き方法と期限
家屋を解体したら、法務局に対して「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」を申請する義務があります。
建物滅失登記とは、登記簿上からその建物が存在しなくなったことを記録する手続きです。この手続きを行わないと、存在しない建物に対して固定資産税が課税され続ける可能性があります。
申請期限は、建物を取り壊した日から1ヶ月以内と定められています。
手続きは自分で行うことも可能ですが、必要書類の準備などが煩雑なため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。解体業者によっては、提携している土地家屋調査士を紹介してくれる場合もあります。
固定資産税に関する注意点
建物が建っている土地には、固定資産税の「住宅用地の特例」が適用され、税額が軽減されています。
しかし、建物を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が翌年から大幅に上がってしまう場合があります(最大で6倍になることも)。
解体後の土地の利用計画(売却、新築、駐車場経営など)を早めに立て、固定資産税の変動も考慮しておくことが重要です。特に、1月1日時点の土地の状況でその年の固定資産税が決まるため、解体のタイミングも考慮に入れると良いでしょう。
解体後の土地活用方法の検討
解体後の土地をどのように活用するかは、事前にしっかりと検討しておく必要があります。
- 売却する
更地にして売却するのか、古家付きで売却するのか、どちらが有利か不動産業者に相談しましょう。 - 新しい建物を建てる
自宅の建て替えや、アパート・マンション経営など。 - 駐車場や駐輪場として活用する
初期投資を抑えて収益を得る方法です。 - 一時的に資材置き場などとして貸し出す
解体前に土地の活用方法を決めておくことで、解体後の手続きや税金対策もスムーズに進められます。
家屋解体に関するよくある質問Q&A
ここでは、家屋解体に関してよく寄せられる質問とその回答をいくつかご紹介します。
- Q1. 解体工事中の騒音や振動はどの程度ですか? 近隣への影響は?
A1. 解体工事では、重機を使用するため、ある程度の騒音や振動は避けられません。しかし、優良な業者は防音シートや養生をしっかり行い、散水するなどして、できる限り近隣への影響を抑えるよう努めます。工事前に業者と一緒に近隣へ挨拶回りを行い、工事内容や期間を説明し、理解を得ておくことが大切です。 - Q2. 近隣への挨拶は自分でするべきですか?
A2. 解体業者と一緒に行うのが一般的で、かつ望ましいです。業者から工事の専門的な説明をしてもらい、施主からは工事への理解と協力を丁寧にお願いすることで、近隣住民の不安を和らげることができます。粗品(タオルや洗剤など)を用意するとより丁寧な印象になります。 - Q3. アスベストの調査費用はどれくらいかかりますか?
A3. アスベストの調査費用は、調査方法(図面調査、現地調査、検体分析など)や建物の規模、調査箇所数によって異なりますが、一般的には数万円~数十万円程度かかることがあります。正確な費用は調査を依頼する業者に見積もりを取って確認してください。2022年4月からは、一定規模以上の解体工事等においてアスベストの事前調査結果の報告が義務化されています。 - Q4. 解体費用はいつ支払うのですか?
A4. 支払い時期や方法は業者によって異なりますが、一般的には「契約時に一部(着手金)、工事完了後に残金」というケースや、「工事完了後に全額」というケースがあります。契約前に必ず支払い条件を確認しましょう。高額な前払いを要求する業者には注意が必要です。 - Q5. 解体工事で出た木材などを自分で再利用できますか?
A5. 基本的には、解体で出た廃材は産業廃棄物として適切に処理する必要があります。もし柱や梁など、再利用したい建材がある場合は、事前に解体業者に相談してください。分別や取り外しに手間がかかる場合、別途費用が発生することもあります。
まとめ
家屋の解体費用は、建物の構造や大きさ、立地条件、付帯工事の有無など、様々な要因によって変動します。
一般的な木造一軒家(30坪程度)であれば、100万円~200万円程度が目安となりますが、これはあくまで概算です。
正確な費用を知るためには、必ず複数の解体業者に現地調査を依頼し、相見積もりを取ることが最も重要です。
見積書の内容をしっかり確認し、不明な点は遠慮なく質問しましょう。
そして、費用を少しでも抑えるためには、
- 家財道具・不用品の事前処分
- 解体工事の時期の検討(閑散期)
- 自治体の補助金・助成金制度の活用
などの方法があります。
家屋の解体は、人生でそう何度も経験することではありません。だからこそ、信頼できる業者を選び、納得のいく形で進めたいものです。
この記事が、あなたの家屋解体に関する不安を少しでも解消し、スムーズな計画の一助となれば幸いです。
まずは、「複数の解体業者に見積もりを依頼する」ことから始めてみましょう。
この記事の担当:

豊栄建設家づくり編集部
家づくりのヒントや住まいの最新情報を分かりやすくご紹介。皆さまの理想の住まいづくりにお役立てください。
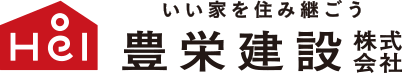

 資料請求
資料請求


 見学ご予約
見学ご予約


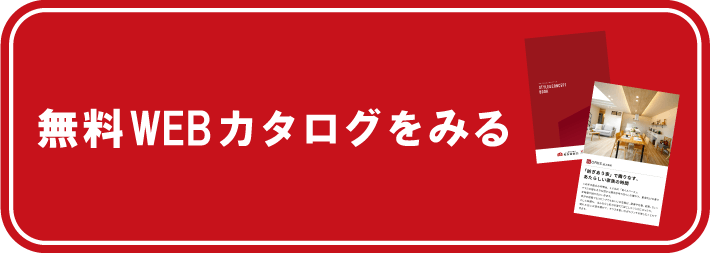
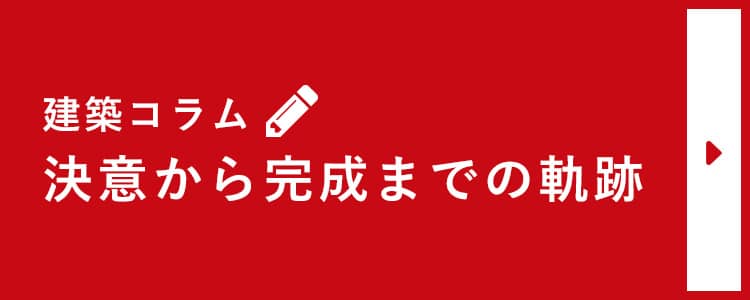









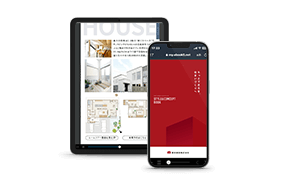




 Facebook
Facebook LINE
LINE Instagram
Instagram YouTube
YouTube

